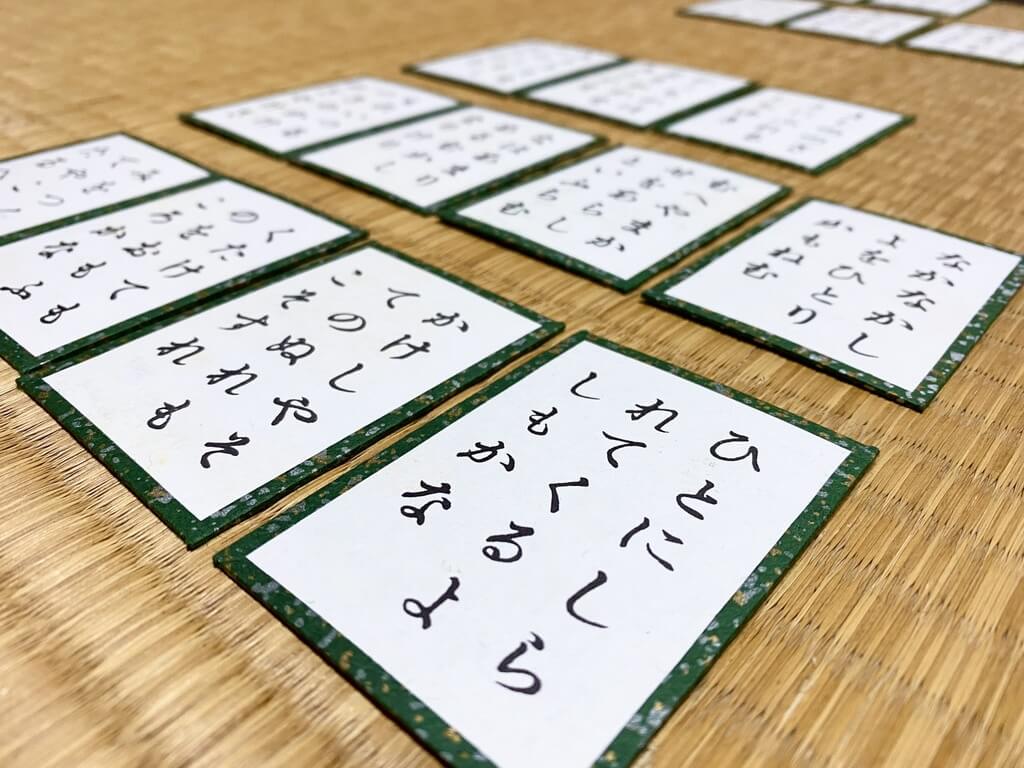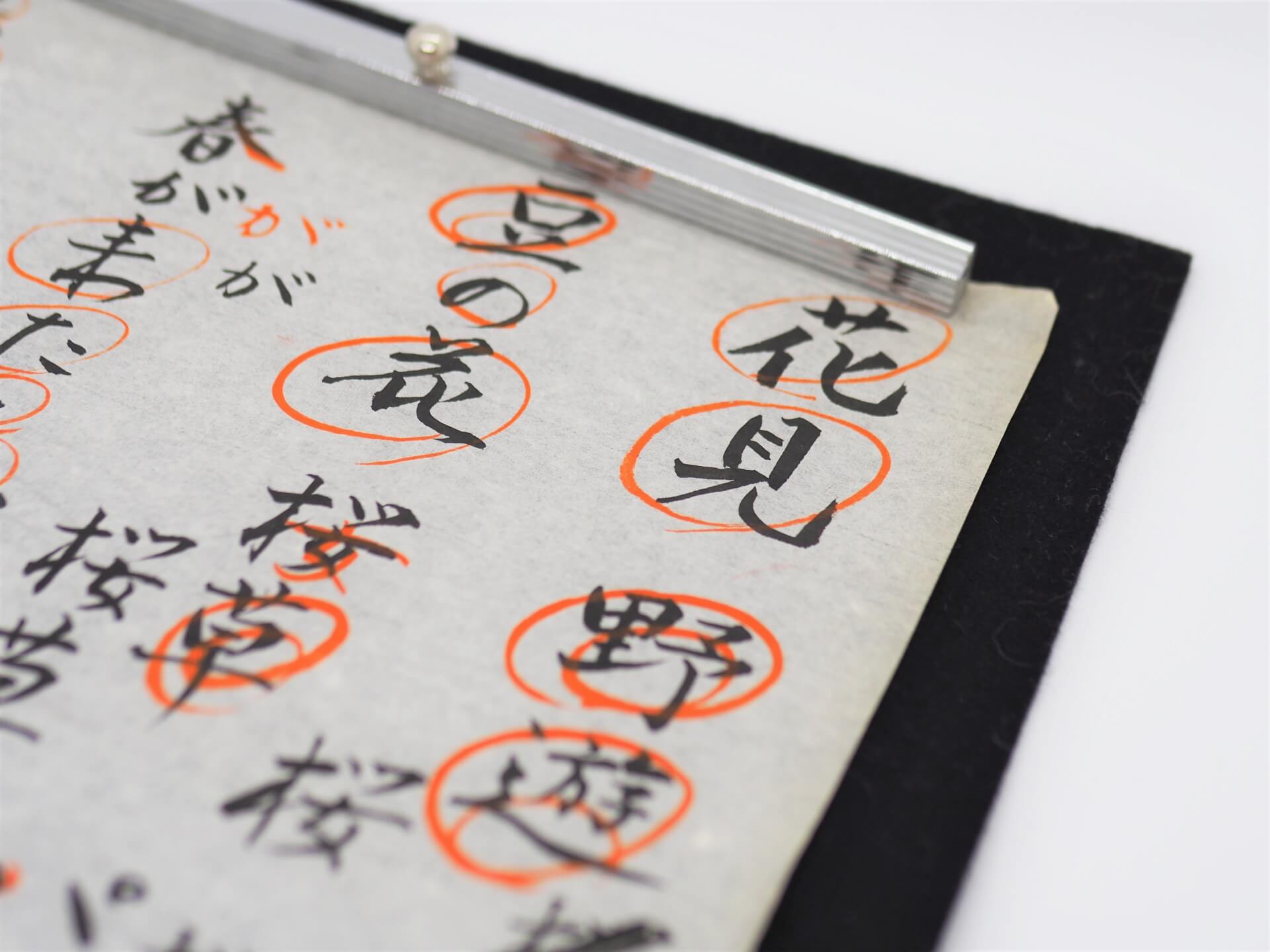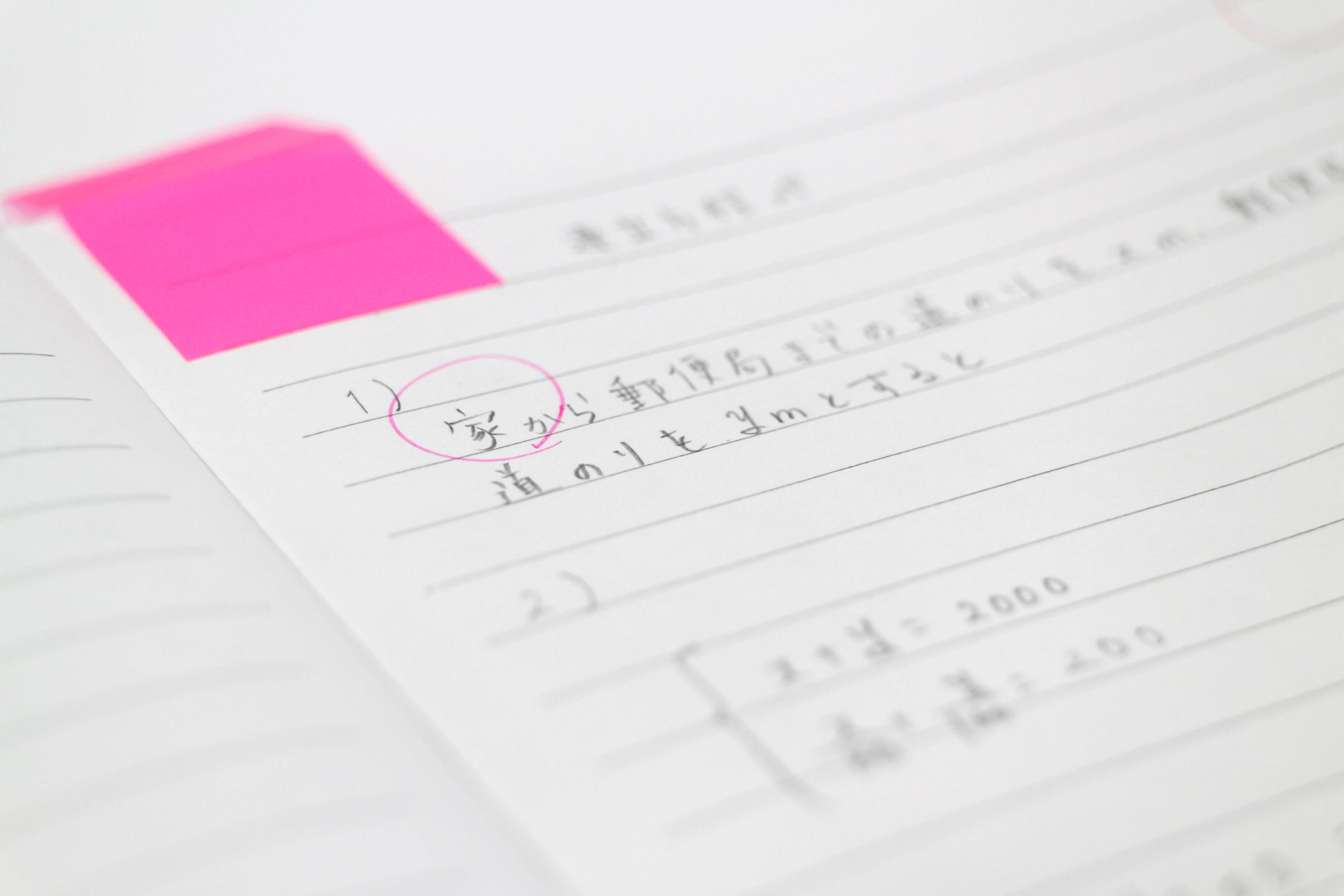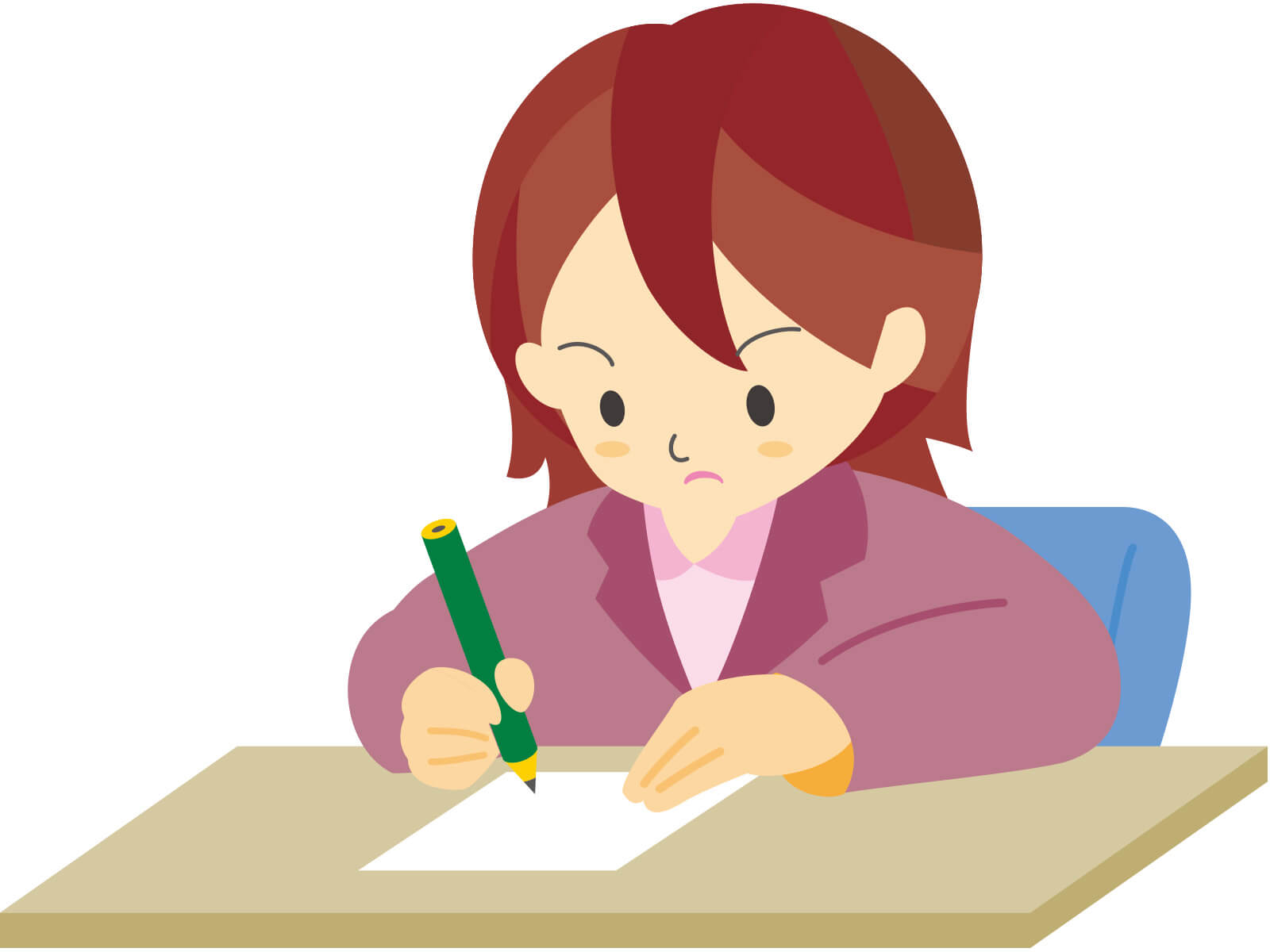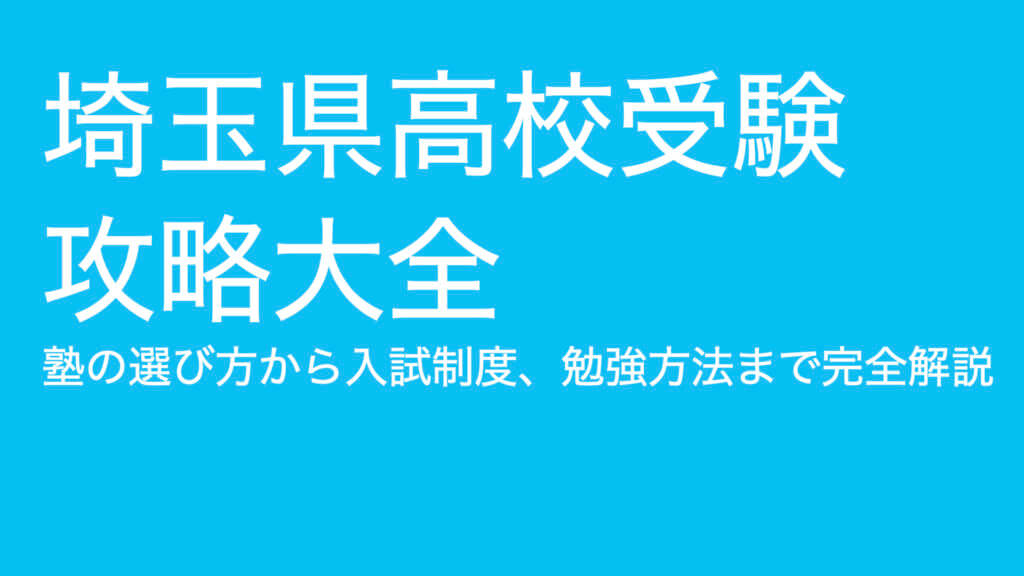定期テストで国語だけ苦手、勉強しても点数が上がらない、という方はこれまで何人も会ってきました。
確かに、毎回初見の文章読解が出題されたら、そうも言いたくなるでしょう。
しかし、定期テストはある程度範囲は決まっていて、さらに出題される内容も予想して勉強することが可能です。
勉強する内容を間違えないで、国語の勉強時間を十分に取れば点数は確実に上がります。
国語が苦手、勉強しても点数が上がらないという人は、これを言い訳にして勉強時間が確保できていない人がとても多いのです。
この記事では国語の勉強方法を具体的にお伝えします。国語で悩んでいる方はぜひ実践してみてください。
まずは漢字を完璧に
まずは、誰もが知っているであろうことです。
しかしながら、私が塾講師をしていた時、漢字練習さえしないで、国語は苦手で点数が取れないと言っていた人もいます。
漢字は10点分近く(多いと20点くらいもありえる)出題されます。多くの場合、担当の先生から出題される漢字は事前に伝えられています。(学校の先生によって異なります)
出る問題がわかっているので、まずそれを完璧にします。単語カードや暗記シートを使うと良いと思います。
知識問題(漢字以外)も完璧に
漢字以外にも簡単に出来る勉強はあります。
国文法、古典、ことわざ、慣用句などの内容を暗記しましょう。
英語と異なり、毎回パターンは同じです。
覚えれば確実に点数が取れるようになります。同じ問題でも構わないので、ワークやプリントを何周もしてください。
ノートやプリントのまとめ直し
さて、いよいよ読解問題編です。
まずは、授業内容を復習しましょう。そこで授業で使ったノートやプリントの登場です。(間が抜けていたり、ちゃんと書けていない場合は信頼できるお友達に借りましょう)
ここで重要なことは、授業(先生の言っていたこと)を「思い出す」ことです。
なぜなら、学校のテストは先生の言ったことが出てくるからです。特に国語は、他の教科よりその傾向が強いです。
授業内容を思い出しながら、ノートをまとめ直してください。まとめた内容がテストに出てきます。自分で問題を作成してみてもいいかもしれません。(この勉強法はいわゆるアクティブラーニングです。他教科でも試す価値ありです。)
音読も超効果あり
さて、音読の効果をご存じですか。
音読は、声帯、鼓膜を使うため運動神経を刺激します。そのため、音読をすると頭に残りやすくなるのです。また、声に出すため適当に読むということが少なくなります。
文章を頭に残すことによって得られる効果は①内容が頭に入っているから設問だけに集中できる②接続語問題に対応できる③文や語句の空欄補充を記憶で解けるです。漢字の読み書きも文章から出題されることもあります。
国語のワークなどを解くと気が付くかと思いますが、パターンとして②や③の問題があります。これらをテスト中に考えるのではなく、記憶で解けたら楽ではありませんか?
入試や模試では、出題される文章がわかっていることはありませんが、定期テスト対策で文章が初めからわかっているので、記憶で解くことが可能です。
文章を読み込まないのは損ですよね。そして、出来れば黙読より音読の方が頭に残りやすいので、声に出した方が良いですよ。
ワーク学習
授業の復習をして、確実に出題される知識をある程度抑えたら、いくつか違ったタイプの問題に着手するのも効果的です。
ここでようやくワーク学習に入ります。
勉強したのに、あまり点数に結びついていないという人は、ここしかやっていないのではないでしょうか。
ここが他教科との大きな差です。他教科はワークからそのまま出題されることが多いですが、国語はそうとも限りません。だから、勉強しても点数が取れないと悩んでしまいます。
あくまでも国語は授業内容重視と覚えておいてください。
ではなぜ、ワークをここで推奨しているのかというと、理由は三つあります。
一つ目の理由は、知識系はここでも復習できるからです。知識系の問題はどの問題でも同じなので、繰り返しの復習で効果があります。
二つ目の理由は、頭の整理です。初めて問われるような設問に対応することで、文章全体をみようとします。授業ノートやプリントの内容だけだと、そこだけしか見えなくなるリスクもあります。全体像も見たうえで、特定の内容を記憶したほうが、前後の結びつくなどが見えやすく、勉強がはかどります。
また、自分の授業を担当をしている先生以外がテストの問題を作成することもあります。そういった対策にもなるので、ワーク学習まで出来ると完璧です。
使うものは教科書ガイドなどが良いと思います。
まとめ
勉強の順序としては、
音読開始
↓
暗記系を完璧にする(※スキマ時間も活用しましょう)
↓
ノートやプリントまとめ(出来たら自作の問題も)
↓
ワーク学習
↓
テスト前には知識事項とノートプリントの確認
となります。ぜひ、やるべきことを明確にして勉強に臨み、高得点を目指してください。
古典の勉強はこちらも参考にしてください↓